こんにちは。書道講師のはな(@hana8family)です。
書道(習字やかきかた教室)は子供の習い事の中で今も昔も王道中の王道。
パソコンやスマホの発達にともなって大人は自分で字を書く機会が少なくなってきましたが、それでも大人になってからでも習いたいと多くの人が思う人気の習い事です。
では子供も大人も書道を習いたいと思った時、教室をどのように選んだら良いのでしょうか。
日本全国には1万以上の書道教室があるそうです。
お住まいの近くをちょっと探してみてください。
すぐにたくさんの教室が見つかると思います。
教室がたくさんあるのは嬉しいですが、どの教室を選べば良いのか迷いますよね。
今日はたくさんある書道教室から自分にピッタリ合った教室を選ぶには何をチェックすれば良いのか、注目すべきポイントを5つご紹介します。
この記事はこんな方にオススメ
- 書道(習字)を習いたい(大人も子供も)
- 子供を書道教室に通わせたい
- 書道教室の選び方が分からない
- 書道教室を選ぶチェックポイントが知りたい
ポイント1:会派や流派は重要!習う内容が違ってくる

茶道や華道など他の芸道と同じように、書道にも会派や流派があります。
「流派にこだわらなくてもどこで習っても書道は書道でしょ?」
と思われるかもしれませんが、

所属する会派や流派によって習う内容が大きく異なるのです!
一般的に「書道教室(習字教室)」といっても、その教室が所属する会派によって、習う内容はざっくり以下のように分かれています。
- 漢字
- かな
- 前衛
- 篆刻
- デザイン書道(現代アート書道)
子供の習字教室は「硬筆」と「毛筆」に分かれているだけです。
が、中学、高校と続けて習う場合、学年があがるほど所属する会派の専門の勉強内容の比重が大きくなっていきます。
特に大人は、展覧会に出品する機会が出てきます。
が、基本的に都道府県規模以上の展覧会には所属している会派の専門部門でしか出品できないルールになっています。(※複数の団体に所属する、もしくは知り合いの先生に頼んで他の部門から出品していただく裏技もあるのですが・・・)
例を挙げてみると、「笹浪会」という大きな会派があります。
ホームページを見てみましょう。
書道笹波会は村上俄山先生のもと、かな書道を研究し、作品を発表する団体です。
と書かれていますね。
そう、笹波会は「かな書道」の会派です。
でもホームページの今月の競書のページを見ると、漢字・かな・ペン字・実用書道のお手本が並んでいます。
つまり、かなも漢字もペン字も習う事ができますが、専門的に掘り下げて勉強するのは「かな書道」で、展覧会に出品できるのも「かな作品」のみということになります。
ですので、「私はかな書道が習いたい!」など学びたい内容がはっきりしている場合は、教室が所属している会派がどこなのか調べてから選びましょう。
幼稚園~小学校の子供に書道を習わせようと思っている場合、どこの教室でも大体同じような内容です。
ですが、子供が長く通いたい場合や大人の方が教室を選ぶ場合、とても重要なポイントとなります。
ポイント2:先生の相性


書道の先生と言っても、厳しい先生、優しい先生、地位の高い先生、教えるのが上手な先生、とてもお金のかかる先生(>_<)など様々です。
では、どのようなタイプの先生なのか具体的にどんな点をチェックすれば良いのでしょうか。
大きく以下の3点にしぼりました。
- 指導が分かりやすいか
- 性格的な相性
- 展覧会活動への姿勢
習い事は教室と長いお付き合いになります。
体験レッスンに参加させてもらえるようなら、是非一度お願いしてみてください。
教室の雰囲気や先生のタイプなどチェックしましょう!
①指導が分かりやすいか
習い事ですので、指導が分かりやすいかどうかは最重要事項ですね。
「先生ご自身はとても優れた技術の持ち主であっても教えるのがヘタ」というのは、もしかして芸術系、勉強系とも先生あるあるなのかも。
②性格的な相性
書道の先生も若い先生から大御所先生まで、男性も女性もいらっしゃいます。
そして厳しい先生もいらっしゃれば、優しく褒めて伸ばすタイプの先生もいらっしゃいます。
これは好みだと思いますので、習われる方の性格に合った先生を探しましょう。
相性が合い尊敬できる先生に出逢えれば、書道を習うモチベーションもアップすること間違いなし。
③展覧会活動への姿勢
展覧会に関しては、教室によって以下3つのタイプに分けられます。
- 展覧会活動はしない
- 展覧会への出品は任意
- 展覧会への出品は強制(もしくは半強制)
展覧会活動はお金と時間と労力がかなり必要になりますので、全く興味がないのに強制的に出品させられると辛いですね。
逆に、展覧会活動をしたいのに全く展覧会活動をしない教室に通ってしまうと、それはそれでストレスになります。
教室を決める時にはぜひチェックしていただきたい項目です。
ポイント3:お月謝はピンキリ
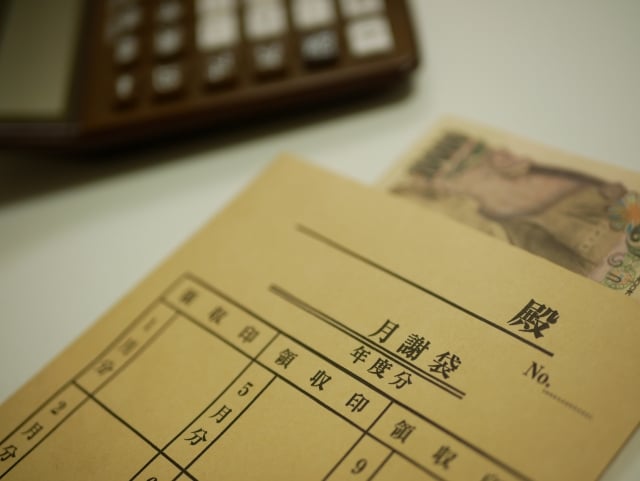
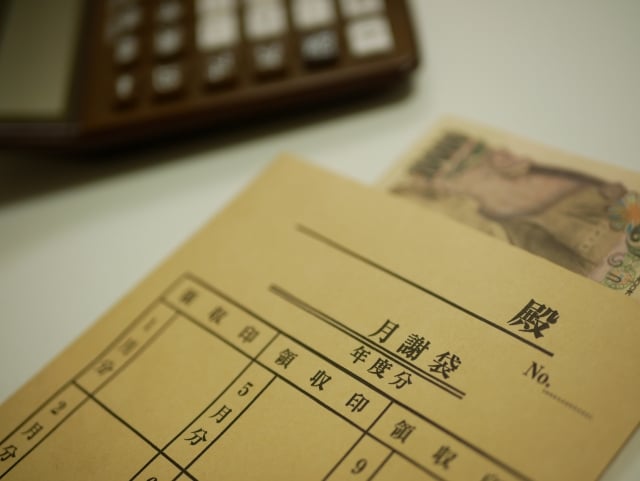
子供の場合
地域にもよりますが、相場は月3000~5000円。
礼儀や文字の基礎をしっかり学ぶ事ができる書道(習字)教室のお月謝は比較的お安めなので、コスパが良い習い事だなと思います。
大人の場合
大人は、ペン字、漢字、かな等習う内容が多い為、月5000~1万円が相場。
有名な先生に教えていただく場合や上段者はお月謝も高くなる傾向。
また大人になると、お月謝以外にも筆や半紙などの道具類に費用がかかります。
段級が上がれば、それに釣り合う道具の購入を求められる事がほとんどです。
あまりに高額な物の購入を勧められないか、納得のいく価格の物を勧められるのか、その点も体験教室などに参加されたら質問しておくと良いですね。
ポイント4:お稽古スタイル
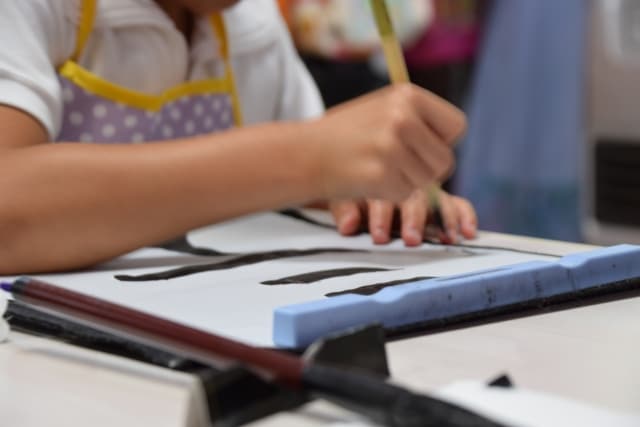
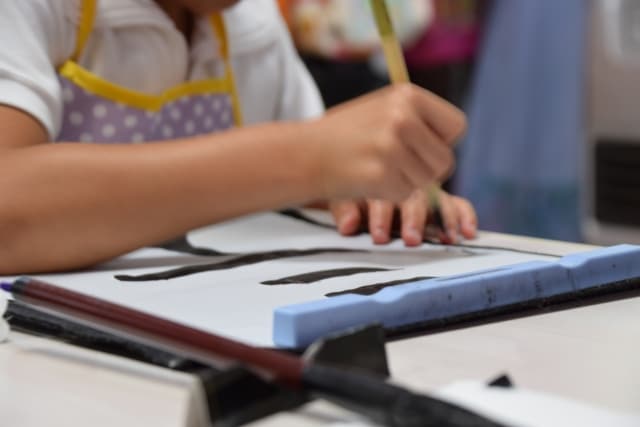
お稽古スタイルはこれという決まりがなく、教室によって様々です。
- 座卓で正座 or 椅子と机
- 個人経営 or 大手企業
- 少人数 or 大人数
①座卓で正座スタイルor椅子と机スタイル
以前は書道教室といえば、ほとんどが床に「正座スタイル」だったのですが、最近はカルチャーセンターや施設など場所を借りて教室を開く方も多く、そういう場合は「椅子と机スタイル」になります。
これが最近案外多い気がします。
②個人経営の書道教室 か 大手企業傘下の経営(例:くもんの書写)
街中で見かける「〇〇書道教室」という看板を掲げる教室は、個人経営の場合が多いと思いますが、「くもんの書写」のような大手企業傘下の教室もあります。
個人経営の場合は、師範免状を取得した先生が、所属する会派の課題に基づいて先生自らがお手本を書いて準備します。
くもんの書写は、公文が配布するお手本プリントを生徒は習います。
メリットは先生の文字の癖が生徒に影響しない事。
デメリットは、先生は書道師範ではない場合もあり、くもんの研修を受けた方が先生ということ。
芸術としての書道を先々学びたい場合は、公文のシステムでは難しいと思われます。
③少人数か大人数
5人以下くらいの少人数で教える教室もあれば、同時に数十人の生徒を教える教室もあります。
人数が多いのに先生が少ない教室は、避けた方が無難かもしれません。
以前近所に月4回2000円という価格破壊的なお月謝で書道教室がオープンしました。
一度に30~40人の生徒を2人の先生で指導されていたのですが、やはり行き届かず「上達しないので行かせる意味がない」と多くの子供が退会しました。
習い事ですので、上達する環境で指導してもらえるのかチェックするのも重要です。
まとめ
ぜひ書道教室を選ぶ際のチェックポイントの参考にしてくださいね!
では(^^)/





